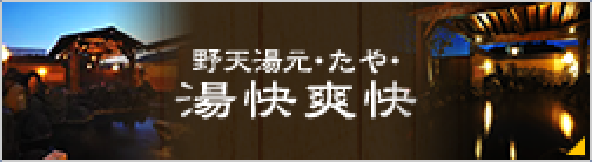平塚エリア
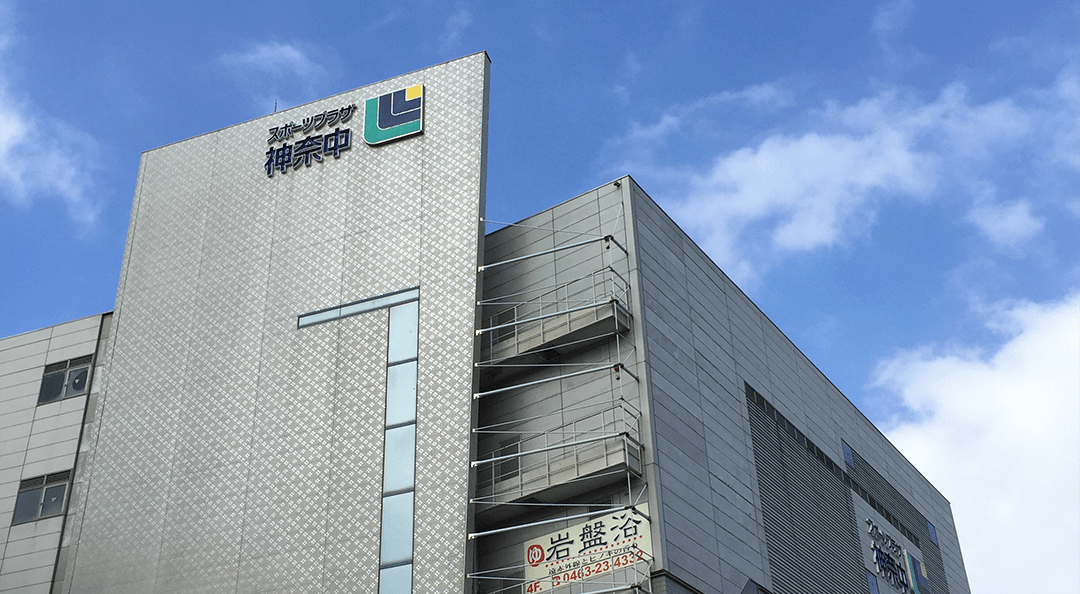
4から6年
【4〜6年生が水泳を始めるメリット】
1. 学校生活や他のスポーツに役立つ理由
筋力・持久力の向上が学習や運動に役立つ
水泳で全身の筋肉を使うと、体幹や腕・脚の筋力がつきます。
体幹が安定すると、座って勉強する姿勢が良くなり集中力が高まります。
持久力がつくことで、体育の授業や運動会、長時間の活動でも疲れにくくなります。
柔軟性の向上がケガ予防や運動能力向上に寄与
肩や股関節、腰の柔軟性が高まると、走る・跳ぶ・投げるなど他のスポーツでの動きがスムーズになります。
柔軟性は転倒や捻挫などのケガの予防にもつながります。
リズム感や協調性がスポーツ全般に役立つ
呼吸や腕・脚の動きを同時に調整する水泳動作は、運動神経の協調性を養います。
この協調性は球技や体操、ダンスなど他のスポーツでもスムーズな動作を生みます。
精神面の成長が学習や生活習慣に影響
水泳では「できるようになるまで繰り返す」経験が多く、諦めずに取り組む力が身につきます。
この挑戦心や集中力は、勉強や日常生活での目標達成にもプラスになります。
2. 勉強に役立つ理由
集中力・注意力が高まる
水泳では呼吸・腕・脚の動きを同時に意識して泳ぐ必要があります。
この「複数のことを同時に意識する力」が、勉強中に机に向かって注意を持続させる力につながります。
脳への血流・酸素供給が増える
水中で全身運動を行うと心拍数が上がり、脳への血流や酸素供給が増えます。
脳が活性化することで、記憶力・理解力・集中力が向上し、勉強効率が上がります。
反復学習と習慣化の力
水泳はフォームや呼吸、タイミングを繰り返し練習するスポーツです。
「繰り返すことで上達する」という経験は、勉強における反復練習や計算・漢字練習の習慣形成にも役立ちます。
自己管理能力の向上
水泳では体調管理・準備・片付け・スケジュール管理を自分で意識します。
自分で計画を立てて取り組む力は、勉強の計画性や時間管理力の向上に直結します。
ストレス解消・精神的安定
水中運動はストレスホルモンを減らす効果があります。
精神的に落ち着くことで、勉強への集中力ややる気が自然に高まります。
💡まとめると、水泳は単なる運動能力アップだけでなく、
「集中力」「記憶力・理解力」「習慣力・計画性」「精神面の安定」につながり、勉強への効果が期待できます。
3. 中学校になると通いにくくなる理由
時間的制約が大きくなる
中学生になると、部活動や定期テスト、学校行事、塾や習い事などのスケジュールで平日・週末の自由時間が少なくなります。
水泳は週1〜2回の定期的な練習が効果的ですが、時間を確保するのが難しく、習慣化が困難になります。
小学生のうちは学習量や課外活動が少ないため、無理なくスケジュールに組み込むことができます。
運動習慣や体力差の影響
小学生時代から運動習慣がある子とそうでない子では、体力・持久力・筋力に差が出てきます。
中学生で初めて水泳を始める場合、周りの運動経験者との差を感じやすく、最初の練習で疲労感や不安を抱きやすいです。
小学生のうちに始めると、成長期にあわせて無理なく体力をつけられ、泳ぎの基礎を自然に身につけられます。
体格の成長によるフォーム習得の難しさ
中学生は身長や手足の長さが個人差大きく、体格の変化が激しい時期です。
初めて泳ぐ場合、手足の使い方やバランスを正しく覚えるのが難しく、効率的な泳ぎの習得に時間がかかります。
小学生のうちは体格差が小さく、基本のフォームを安定して覚えやすいです。
精神的ハードルの増加
中学生になると、恥ずかしさや「人に見られることへの抵抗感」が強くなります。
「プールでうまく泳げなかったらどうしよう」といった不安から、最初の一歩を踏み出すことが心理的に難しくなる場合があります。
小学生のうちは好奇心や挑戦心が強く、安心できる環境であれば自然に挑戦できます。
他の習い事・スポーツとの兼ね合い
中学生になると、部活や他の習い事とのスケジュール調整が必要になり、水泳を新しく始める優先順位を下げざるを得ないケースがあります。
小学生のうちはスケジュール調整がしやすく、継続的に通うことで基礎体力や泳力の向上が期待できます。
モチベーション維持の難しさ
初めて水泳を始める中学生は、周囲の泳力が高い場合に自己評価が下がりやすく、やる気を維持しにくい傾向があります。
小学生のうちに始めれば、少しずつステップアップして成功体験を積み重ねられるため、モチベーションが続きやすいです。
お問い合わせ・無料体験はコチラ